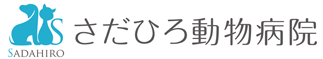
047-700-5118


診察時間
午前9:00-12:00
午後15:00-18:00
手術時間12:00-15:00
水曜・日曜午後休診

NEWS&BLOG
犬の口腔内腫瘍 メラノーマ
※手術の写真があります。
口腔内腫瘍は、悪性腫瘍の場合では進行度の早いものが多く、早期診断が必要な病気にもかかわらず、口腔内の奥に発症した場合は、発見が遅れがちになります。
また、犬で1番多いと言われるメラノーマは転移の速度が速く、発見時には多くの子が転移を起こしていると言われています。
大きくなるのも早く、顎骨に浸潤し、疼痛で食べられず、衰弱してしまったり、出血や感染を繰り返します。
猫では扁平上皮癌が多く、広く顎骨に癌細胞が浸潤してしまいます。
口腔内の癌に対しては、腫瘍のみを小さく取る手術ではすぐに再発してしまうため、顎骨を含めて大きく切除する必要があります。
再発した腫瘍は初回発生の腫瘍に比べて進行速度攻撃性が高いので、最初の手術で腫瘍と正常組織を一部含めて大きく切除する事が重要です。
手術の目的は、この病気にかかってしまったわんちゃん、ねこちゃんが痛みを感じずに、ごはんを食べれるようにすることです。
腫瘍を切除する時に、近くのリンパ節を切除し、腫瘍の転移がないかも評価しています。
また、術前には肺のレントゲンを撮って、肺転移がないかも評価しています。
口腔内腫瘍はサイズによって外科手術後の生存期間が大幅に変わってきます。
2cm未満で切除できると1年以上の生存が期待できるといわれますが、そのサイズで発見出来ることが難しいのが現状です。
下顎にできた腫瘍の場合はあまり外観が変わらない事が多いです。
犬の場合は、翌日から食事の給餌を開始しています。
猫は術後の疼痛から食べられない事が多いので、食道チューブの設置も併用することがあります。




