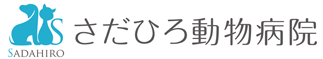-
-
抗生剤でも治らない鼻炎について
鼻炎が抗生剤で改善しない場合、原因として耐性菌の感染や、見逃されがちな鼻腔内腫瘍が考えられます。猫では、長期間の抗生剤投与にもかかわらず症状が改善しない場合、腫瘍の可能性があり、併せて抗菌剤の選択試験も推奨されます。特に麻酔が困難な場合は、鼻腔粘膜の細胞診と癌遺伝子検査を組み合わせた負担の少ない検査が行われます。
-
-
症状の詳細
鼻炎の症状には食欲不振、異常な呼吸音、顔の腫れ、鼻血、目やにや涙が多くなるなどがあります。特に食事時に苦しみ、徐々に食べる量が減ることや、口呼吸が主になることで胃の膨張や嘔吐を引き起こすことがあります。
-
-
検査方法について
診断には細菌培養同定・薬剤感受性検査、レントゲン検査、鼻腔のバイオプシーなどが含まれます。これらの検査により、感染している細菌の種類と効果的な抗生剤、鼻腔内の腫瘍の有無やその大きさ、位置、病理学的な詳細が明らかになります。無麻酔で行える検査もありますが、より確実な診断のためには麻酔下での検査が必要な場合もあります。
-
-
猫の鼻腔内腫瘍について
猫の鼻腔内腫瘍の約30%がリンパ腫で、その多くが猫白血病ウイルス(FeLV)や猫免疫不全ウイルス(FIV)とは無関係です。リンパ腫は腎臓への転移が見られやすいため、超音波検査で確認が必要です。治療法には放射線治療、抗がん剤治療、対症療法がありますが、リンパ腫でも、抗がん剤が効くBcellタイプと、効かないTcellタイプがあるので、外部の検査センターへ「クローナリティ解析」を依頼し、鑑別します。