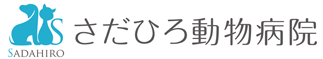
診察時間
午前9:00-12:00
午後15:00-18:00
手術時間12:00-15:00
水曜・日曜午後休診

肝臓の腫瘍🥩
-
-
肝臓・胆管の腫瘍の概要
肝臓・胆管の腫瘍は肝臓・胆管由来の原発性腫瘍と、他臓器からの転移性腫瘍に分類されます。原発性肝臓・胆管腫瘍は良性・悪性にわかれ、一方、転移性肝臓腫瘍は全て悪性であり(特に脾臓、膵臓、消化管からの転移が多い)
、予後は不良です。原発性の腫瘍は稀で、転移性の方が多く、発生率に2.5倍の差があります。
| 発生率 | 犬の肝臓腫瘍 | 猫の肝臓腫瘍 |
|---|---|---|
| 1 | 肝細胞癌(肝細胞腺腫) | リンパ腫 |
| 2 | 結節性過形成 | 胆管癌、胆管腺腫 |
| 3 | 転移性腫瘍 | 結節性過形成 |
| 4 | リンパ腫 | |
| 5 | 原発性血管肉腫 | |
| 6 | 胆管癌 |
-

-
原発性悪性腫瘍
組織学的には、肝細胞か、胆管、神経内分泌、間葉由来のいずれかに分類されます。形態学的には大きな塊を作る塊状のタイプ、結節タイプ、浸潤するタイプの3つに分類されます。
-
-
肝細胞癌
肝臓細胞由来の腫瘍の一つで、犬では最も発生率が高い(約50%)が悪性腫瘍に分類されます。転移率にはばらつき(4%)があります。肝細胞癌の症状に特異的なものはなく、食欲がなくなったり、体重が減ってきたり、腹水がたまる事が多いです。重度の場合には黄疸や、意識がなく、発作を起こすような、肝性脳症などもありますが、無症状でも、偶然発見されることがあります。
診断には超音波検査、CT検査、生検、病理組織学的診断などが使用されます。塊まりを作るタイプの肝細胞癌の患者さんは、外科切除を行うことで、2年以上の生存期間の延長ができると報告されています。一方で、手術を受けなかった患者の余命は1年未満になることが示されています。塊状型の肝細胞癌は多くの場合、手術により予後が改善されます。しかし、結節型または浸潤型の肝細胞癌は、多発性に存在するため、外科手術が困難で、予後は不良です。
-
-
肝細胞癌以外の腫瘍
胆管癌は外科切除自体が困難な事が多く、予後は不良です。また、カルチノイドは激しい腫瘍であり、外科切除は適応されません。犬においては、リンパ節、腹膜、肺に転移する可能性が高いため、予後は不良です。
早期発見のために、高齢のわんちゃんでは、健康診断の際に、血液検査に、腹部のエコー検査を加えることで早期診断の助けになります。
-
-
術後管理
オピオイドが有効であり、抗菌薬の投与が必要です。肝臓には嫌気性菌が常在する可能性があるため、術後もしっかり輸液を行い、乳酸リンゲル液+ビタミンB製剤+肝庇護薬の積極的な栄養支持を行います。術後2〜3日は血液検査でモニターします。
-
-
術後の合併症
出血、貧血、膵炎→DIC、感染、肝不全(70%までの肝切除であれば通常は発生しない)などがあります。
