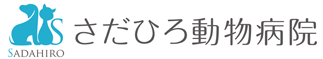
047-700-5118


診察時間
午前9:00-12:00
午後15:00-18:00
手術時間12:00-15:00
水曜・日曜午後休診

NEWS&BLOG
胃拡張・胃捻転症候群(GDV)
-
-
胃拡張胃捻転症候群の発症と緊急性
胃拡張胃捻転症候群(GDV)は、特に大型犬に見られる重篤な状態で、胃が拡大し、さらに捻転することで、内部の血流が遮断され、急速に生命を脅かす状況に至ります。治療が遅れると胃壁の壊死が進行し、脾臓と胃の間の血管が断裂して重篤な出血を引き起こす可能性があります。
-
-
検査所見と内科処置
GDVの初期検査ではX線により胃の拡張と捻転の確認が行われます。内科的治療としては、輸液療法による循環支持と衝撃の管理が重要です。緊急性が高いため、速やかに輸液を開始し、胃内圧の低下を図ります。
-
-
外科処置と合併症
外科的には、胃と場合によっては脾臓の位置の修正、壊死組織の除去が行われます。不整脈や凝固障害などの合併症が手術後に頻繁に見られ、これらは死亡率を高める要因となり得るため、継続的なモニタリングが必須です。
-
-
術後管理と予後
術後の管理では、定期的な心電図検査による不整脈の監視、腎機能と凝固プロファイルの評価が行われます。回復期には消化を助けるため流動食から開始し、徐々に通常食へと移行します。GDVの予後の生存率は手術の迅速性と初期の適切な管理に強く依存します。
